
用語集
サ行
最小土被り (さいしょうどかぶり)(テールアルメ用語)テールアルメ工法は摩擦効果を期待するため、ストリップの上面に必ずある一定以上の土などの重量、すなわち土被り厚が必要となる。最小土被り厚とはスキン上端より盛土仕上げ面までの高さをいう。 |
|
細粒分 (さいりゅうぶん)粒径が75μm(1μmは1000分の1mm)以下を細粒分という。粘土分、シルト分がこれに該当する。細粒分が50%より多い土を細粒土という。 |
|
サウンディング (さうんでぃんぐ)原位置で行なう試験で、ロッド先端に取り付けた抵抗体を地中に挿入して、貫入、回転、引き抜き抵抗値などから土の強さを推定する。代表的なものは標準貫入試験、コーン貫入試験など。 |
|
三軸圧縮試験 (さんじくあっしゅくしけん)土の強さを調べる試験。土圧、支持力など地盤や盛土の安定計算に用いられる粘着力(c)、内部摩擦角(Φ)が得られる。円筒形の供試体に薄いゴム膜を被せて側圧を作用させ、供試体が破壊するときの垂直応力を測定する。強度特性を把握するため、側圧を変化させそれぞれの垂直応力を測定する。圧密・排水条件の違いによって、UU・CU・CDなどの試験がある。 |
|
サンドイッチ工法 (さんどいっちこうほう)(テールアルメ用語)テールアルメ工法のストリップに接する部分を、良質の粗粒土で囲むことでストリップと盛土材の摩擦効果を改善する方法である。 |
|
試行くさび法 (しこうくさびほう)土圧計算の手法。土塊のすべり面角度を試行的に変化させて作用する最大の主働土圧Paを求める手法。 |
|
支持力 (しじりょく)地盤が上載荷重を支える能力を支持力という。通常、単位面積あたりの応力で表記する。極限支持力、許容支持力など。 |
|
自然含水比(Wn) (しぜんがんすいひ)自然状態にある土の含水比を呼び、土の種類によって大きく異なる。一般的に自然含水比の値は粗い土粒子を多く含むほど小さく、細かい土粒子を多く含むほど大きい傾向を示す。 |
|
締固め(土の) (しめかため(つちの))土に何らかの荷重を加え、土中の間隙を小さくして地盤の密度を高めることを土の締固めという。 |
|
締固め曲線 (しめかためきょくせん)土を締固める場合の含水比と乾燥密度との関係を示す曲線。一定の締固め方法で土の含水比を増加(減少)させながら締固めてそれぞれの乾燥密度をプロットする。最大乾燥密度ρdmaxが得られる含水比を最適含水比Woptと呼ぶ。 |
|
| ページトップへ | |
集中荷重 (しゅうちゅうかじゅう)荷重がほぼ1点に集中して作用すると考えられる場合、この荷重を集中荷重とよぶ。 |
|
主働土圧 (しゅどうどあつ)構造物が動こうとする際にもたれかかるように作用する土圧。 |
|
主働土圧係数 (しゅどうどあつけいすう)主働土圧と土被り圧の比 |
|
主働領域 (しゅどうりょういき)(テールアルメ用語)敷設されたストリップの応力の最大引張線を考慮した想定境界線から壁面側にある領域を呼ぶ。設計上、主働領域内ではストリップは抵抗しないとしている。 |
|
地震時の増加係数 (じしんじのぞうかけいすう)地震時のストリップに作用する水平力の常時に対する増加比率。実験などで定められたテールアルメ固有の係数。 |
|
地滑り (じすべり)地質構造的要因によって斜面が比較的広範囲にわたり滑動するものをいう。地滑りには滑動が長期間に及びしかも緩慢なものが多い。浅いボーリング調査では判別できない場合もある。 |
|
実行ストリップ長 (じっこうすとりっぷちょう)内部安定、外部安定によって決定された実際に敷設されるストリップの長さ。 |
|
地盤改良 (じばんかいりょう)地盤改良とは、地盤の工学的性質を人工的に安定化させることをいう。地盤改良には土の密度を増大させる方法(サンドコンパクションなど)、固結する方法(固化材混合改良など)、補強する方法の三種類がある。 |
|
ジベル筋 (じべるきん)(テールアルメ用語)コンクリートスキンの袖部に設けられているスキン接続用の突出鉄筋。同じくコンクリートスキンの袖に開けられているシースと呼ばれる孔に挿入する。 |
|
縦断勾配 (じゅうだんこうばい)道路などの坂のきつさを示したもので、通常パーセントで呼ぶ。延長に沿った水平長さに対する鉛直高さの比率である。 |
|
| ページトップへ | |
受働土圧 (じゅどうどあつ)構造物を土の方向に移動させたときに構造物に作用する土圧。 |
|
受働土圧係数 (じゅどうどあつけいすう)受働土圧と土被り圧の比 |
|
純断面積 (じゅんだんめんせき)ストリップにおけるボルトの孔および腐食しろを控除した断面積。 |
|
水平目地 (すいへいめじ)壁面部などにおける上下スキンの水平方向目地部。 |
|
水平目地材 (すいへいめじざい)(テールアルメ用語)コンクリートスキンを組み立てる際に水平目地部に設置する収縮性のあるクッション材。壁面全体の柔軟性を確保するために用いる。従来はコルクプレートを用いていたが、現在ではゴム製プレートを用いている。 |
|
水辺テールアルメ (すいへんテールアルメ)(テールアルメ用語)河川、湖沼、池や海岸等の水辺に直に接して構築されるテールアルメをいう。設計においては水による補強材の耐久性、流速や波浪による基礎部の洗掘や盛土材の流出、残留水位によって生じる水平力などに対する検討が必要な場合がある。 |
|
スキン (すきん)壁面材の一般呼称。コンクリートスキン、コーナースキン、メタルスキンなど。 |
|
スキンエレメント (すきんえれめんと)(テールアルメ用語)テールアルメの壁面材の総称。コンクリートスキン、メタルスキン、コーナースキンなどという。 |
|
スキンの割付け (すきんのわりつけ)壁面の展開図にスキンを組み合わせて、詳細な使用スキンタイプを決定すること。 |
|
ストリップ (すとりっぷ)盛土内に敷設するテールアルメの補強材の総称。リブ付きストリップ、高強度リブ付きストリップ、平滑ストリップなどがある。 |
|
| ページトップへ | |
滑り破壊 (すべりはかい)土塊が直線状あるいは円弧状に滑るように破壊する現象。テールアルメ工法を含む盛土全体の基礎地盤および盛土斜面に対する安定検討は、一般に分割法による円弧すべり面法によって計算し安全性を判断する。 |
|
スレーキング (すれーきんぐ)塊状の岩石が、地下水などの影響により乾燥湿潤が繰り返されることによって、時間の経過とともに徐々に細粒化する現象。盛土の完成後に長期にわたって圧縮沈下を生じる事などがあり注意が必要。泥岩、頁岩、凝灰岩、片岩などが対象となる。 |
|
静止土圧 (せいしどあつ)静止した状態での土圧。 |
|
設計寸法 (せっけいすんぽう)内部安定や外部安定で使用する、設計上の寸法。 |
|
せん断強さ (せんだんつよさ)土がせん断破壊する時のせん断応力の最大値。せん断強さΤ(たう)は、せん断抵抗角Φ粘着力cとせん断面に働く垂直応力σを用いて、次式のように表わす。 ’Τ=C+σ・tanΦ |
|
せん断破壊 (せんだんはかい)せん断応力によって生ずる破壊現象。地盤支持力、斜面安定、土圧等の力学における現象はせん断力に関連づけられるものである。 |
|
全応力法 (ぜんおうりょくほう)斜面の安定解析などで用いられる解析法のうち強度定数を全応力で与える方法。多くの場合地盤内の過剰間隙水圧を充分想定できないため、最も危険側の排水条件である全応力に関する強度定数で解析する。 |
|
総断面積 (そうだんめんせき)ストリップにおける腐食しろを控除した断面積。 |
|
即時沈下 (そくじちんか)地盤の沈下において、せん断変形や、側方流動によって生ずる沈下。圧密排水による沈下に先立って生じる現象。 |
|
塑性限界 (そせいげんかい)細粒土のコンシステンシー限界の一つ。土質によって異なる土の軟らかさ(硬さ)程度を分類する含水比。土が半固体から塑性状態に移行する時の含水比(PL)。 |
|
| ページトップへ | |
外曲がり (そとまがり)(テールアルメ用語)テールアルメ壁のコーナー部でコーナーをはさんだ左右の角度が、盛土側から測って180度よりも大きいものを呼ぶ。反対語:内曲がり |
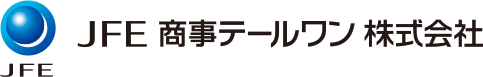
 各種ダウンロード
各種ダウンロード





